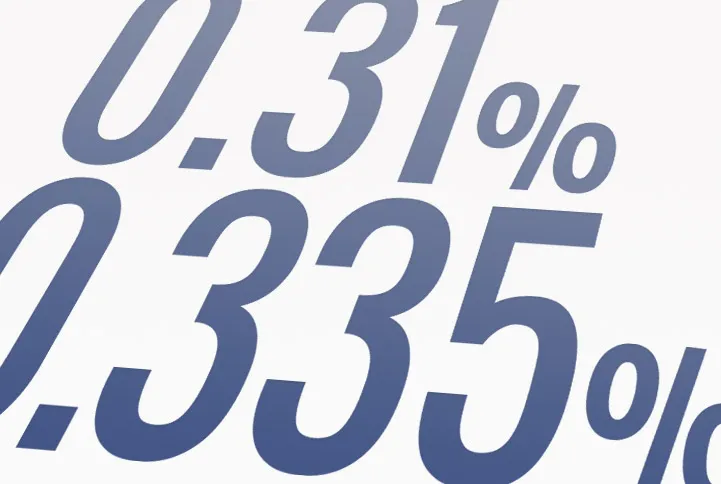関税ってなに?基礎知識からトランプ関税まで解説!

情報コラム
2025年7月29日
ニュース等で「関税」や「トランプ関税」という言葉を耳にすることがありますが、具体的に何を指しているかご存知でしょうか。
聞いたことはあっても、ご自身の生活への影響まで意識している方は少ないかもしれません。
関税は企業だけでなく私たち消費者の日常生活にも影響を及ぼす可能性があるため、基本を理解し
ておくことが大切です。
そこで本記事では、関税の基礎知識からトランプ関税まで、わかりやすく解説します。
関税とは?

まずは、関税の目的や仕組みといった基礎知識を確認しておきましょう。
関税の基本的な仕組み
関税は、外国から商品を輸入するときに課される税金です。
商品が国内に入るタイミングで税関が税額を確定し、輸入先の政府に納付します。
【納税者と負担者】
関税の納税者は基本的には「輸入者」です。
ただし、関税額は商品の価格に上乗せされることが多いため、実質的に関税を負担しているのは「消費者」ということになります。
例)日本企業が中国から衣料品を輸入する場合
納付先:日本政府
納税者:日本の輸入企業
負担者:日本国内でその衣料品を購入する消費者
【関税の目的】
関税には、主に以下のような目的があります。
(1)自国産業の保護
関税をかけることで輸入品の価格が上昇するため、相対的に国内製品が割安になり、消費者に選ばれやすくなります。
これにより、国内企業は海外製品との過度な価格競争に巻き込まれずに、適正な価格を維持しやすくなります。
(2)財政収入の確保
関税収入は、国の財源の一部として利用されています。
ただし先進国では、消費税や所得税等、他の税収の割合が高いため、全体に占める関税収入の比率は低くなっています。
【関税率】
関税率は輸入品の種類や原産国によって異なります。
つまり、同じ商品でもどこの国から輸入するかによって、適用される関税率が変わるケースもあるということです。
自由貿易協定(FTA)や経済連携協定(EPA)を結んでいる国との取引では、関税が引き下げられたり、無税になったりすることもあります。
【関税率の形態】
関税は、輸入品の「価格」または「数量」をもとに算定されます。
価格をもとにしたものを「従価税」、量をもとにしたものを「従量税」といいます。具体例は下記のとおりです。
例)
従価税:10万円の商品に10%の関税 → 税額は1万円
従量税:1kgあたり200円の関税 → 5kgなら1,000円
また、従価税と従量税を組み合わせた「混合税」という形態もあります。
日本ではほとんどの品目で従価税が適用され、従量税は特定の品目に限られます。
関税と消費者の関係
前述のとおり、実質的に関税を負担しているのは消費者です。
というのも、輸入業者が支払った関税は、そのまま商品価格に上乗せされることが多いからです。
なかには企業努力によって関税の一部を自社で吸収するところもありますが、基本的には輸入商品の価格には関税分が上乗せされていて、消費者が負担していると考えましょう。
関税による影響

関税は、経済活動や国際情勢等にも様々な影響をもたらします。
特に日本のように資源や食料の多くを輸入に依存している国では、関税率の変化が物価や家計に直接的な影響を及ぼすこともあります。
ここからは、関税が与える影響について具体的にご説明します。
輸入品の値段への影響
関税は、輸入品の値段にダイレクトに影響します。
先にもご説明したとおり、輸入品が国内で販売される際の価格は、「仕入れ価格+関税額」をもとに決定されるからです。
そのため、関税の引き上げは、輸入品の価格上昇の要因となります。
特に、食料品や日用品といった生活必需品に高い関税がかかれば、家計の負担が増し、消費者の購買意欲が低下する可能性があります。
こうした状況が続くと、国内市場にまで影響が及び、経済の停滞につながるリスクもあります。
反対に、関税の引き下げは、輸入品の価格下落の要因となります。
原材料や部品等を輸入に頼っている企業の製品も値下がりし、消費者はより手頃な価格で購入できるようになります。
その結果、消費者の購買意欲が高まり、企業の売上増加や国内経済の活性化につながります。
国内産業への影響
関税は、国内産業にも影響を与えます。
関税が上がると輸入品の価格が高くなり、相対的に国産品の方が安くなるため、消費者は国産品を選びやすくなります。
その結果、国内産業の売上維持や雇用の安定につながる効果が期待できます。
一方で、関税の引き上げによって国内産業が過度に保護された状態が続くと、企業同士が競争意識を持ちづらくなり、技術革新やサービス改善が停滞するおそれもあります。
また、製品の原材料や部品を海外から仕入れている企業にとっては、関税を引き上げることで調達コストが増え、製品価格の上昇や利益の圧迫といった形で負担となることもあります。
逆に関税が引き下げられると、海外製品が安価で流通するようになり、消費者は国産品よりも海外製品を選びやすくなる可能性があります。
そのため、国内企業は価格や品質、サービス等、様々な面で海外企業と競争しなくてはいけません。
競争力の弱い分野では、売上の減少や事業の縮小といった影響が出ることも考えられます。
貿易摩擦
関税は、国同士の関係を左右し、各国の経済にまで影響を及ぼすことがあります。
たとえば、ある国Aが自国の産業を保護するために関税を引き上げて輸入を制限しようとすると、貿易相手国Bは自国の商品が輸出先で売れにくくなる、輸出コストが増加する等の不利益を被ります。
そのため、国Bも対抗措置として関税を引き上げ返すと、さらに国Aが関税を引き上げるといったケースも少なくありません。
こうしてお互いに関税を引き上げ合う状態になると、双方の貿易が停滞し、経済にまで悪影響が及ぶのです。
実際、近年でもアメリカと中国の間で高関税をめぐる対立が起こっており、両国間の貿易量が減少する等、世界経済にも影響を与えました。
関税は本来、国内産業を守るための政策手段ですが、使い方によっては国際関係を悪化させ、自国の経済にも悪影響を及ぼす可能性があるため、慎重な対応が求められます。
トランプ関税

最後に、アメリカのトランプ大統領による関税政策と、日本への影響等をご紹介します。
トランプ政権の関税政策
2025年1月に第2次トランプ政権が発足して以降、アメリカは貿易赤字の縮小と国内産業の保護を図るため、相次いで関税引き上げ策を実施しました。
各国との交渉等により内容は変わる可能性がありますが、2025年6月末時点での、トランプ関税の概要は下記のとおりです。
・中国の輸入品に30%、カナダ、メキシコの輸入品に25%の追加関税(一部除外品目あり)
・鉄鋼・アルミニウム製品に50%の追加関税
・自動車、部品類に25%の追加関税
・全輸入品に一律10%の基本関税+国別に相互関税の上乗せ
相互関税
相互関税とは、輸入国が課している関税と同じ水準で、相手国からの輸入にも同等の関税を課す制度です。
たとえば、日本がアメリカからの輸入品に10%の関税をかけている場合、アメリカも日本からの輸入品に10%の関税をかける、というものです。
この政策は、トランプ政権が掲げる「フェアな貿易」の実現を目指して打ち出したもので、相手国がアメリカ製品に高関税を課している場合、アメリカも同様の関税を課すことで、取引条件の対等化を図ろうという意図があります。
2025年4月、アメリカは57の国と地域に対する相互関税率を発表し、日本については24%と算定しました。
ただしこの関税率は暫定的で、2025年6月時点でも日本政府による税率緩和に向けた交渉が行われています。
日本への影響
日本は自動車や電気機器をはじめ、輸出額が多い品目を多く抱えており、これらに高関税がかけられた場合の影響は避けられません。
特に自動車関連はアメリカ市場への依存度が高く、高関税が長期化すれば輸出価格が上昇し、売上の減少やシェアの低下、収益悪化が起こり得ます。
国内雇用の悪化や経済成長にも影響が及ぶ可能性が考えられます。
まとめ

日常生活のなかで関税を意識する場面は少ないかもしれませんが、実は関税は我々の生活にも大きな影響を及ぼす可能性があります。
また、トランプ政権のように大幅な関税引き上げや相互関税制度の導入が進められると、国内企業や日本経済全体への影響も避けられません。
こうした国際情勢の変化に対応していくためには、経済の基礎知識を持っておくことはもちろん、資産の守り方を意識しておくことが大切です。
ご自身に合った資産の守り方が知りたい方は、銀行や証券会社等で専門家に相談するといいでしょう。
資産運用のご相談は西武信用金庫へ
西武信用金庫ではお客さまの資産運用のご相談を承っております。