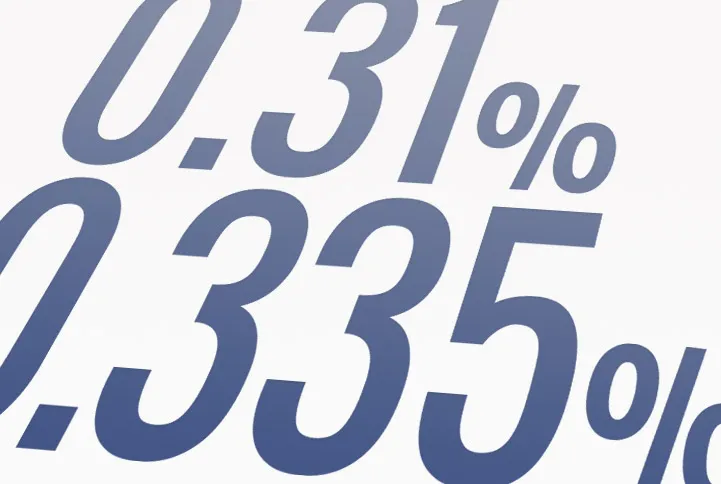給与明細は、毎月の給与の内訳が記載された重要な書類です。
給与明細の内容を理解し、ご自身の収入や支出をより詳しく把握することで、家計管理や将来の資産形成に役立てることができます。
そこで本記事では、給与明細の基本的な見方や確認すべきポイントについて、わかりやすく解説します。
給与明細の基本項目と見方のポイント

会社によって様式に多少の違いがありますが、給与明細は一般的に「勤怠」「支給」「控除」の3つの項目で構成されています。
まずは、各項目の概要とチェックすべきポイントを確認しておきましょう。
勤怠項目
勤怠欄に記載されているのは、締め日までの1ヵ月間の出勤日数や勤務時間、休暇に関する情報です。
会社により多少違いはありますが、主に下記のようなことが記載されています。
・出勤日数
・欠勤日数
・残業時間(平日残業、深夜残業)
・休日労働時間
・有給消化日数
・有給残日数 等
勤怠項目に記載の内容は、給与の支払い日ではなく締め日までの情報である点に注意しましょう。
支給項目
支給欄には給与のベースとなる基本給のほか、各種手当や残業代等、その月に会社から支払われる金額の内訳が記載されています。
支給項目の具体例は下記のとおりです。
・基本給
・残業代
・役職手当、資格手当
・通勤手当
・住居手当
・家族手当、扶養手当 等
控除項目
控除欄には、給与から天引きされる税金や社会保険料等が記載されています。
控除項目の具体例は下記のとおりです。
・社会保険料(健康保険料、厚生年金保険料、介護保険料、雇用保険料)
・所得税
・住民税
・社内預金、積立金(財形貯蓄・社員旅行積立・共済会費等)
確認すべき箇所
給与明細で特にしっかり確認しておきたいのは、下記の箇所です。
・残業時間、休日労働時間に誤りがないか
・有給消化日数、残日数は合っているか
・勤怠内容と手当の金額にズレがないか
・明細に記載の金額と、振り込まれた金額が一致しているか
これらを確認し、もし誤りがあった場合は会社の担当部署に問い合わせましょう。
特に問題がなかった場合でも、念のため給与明細は5年ほど保管しておくことをおすすめします。
ローンやクレジットカードの申し込み時に提示を求められることもあるためです。
法的な保管義務はありませんが、万が一のことを考えると保管しておくのが安心でしょう。
給与から天引きされるお金
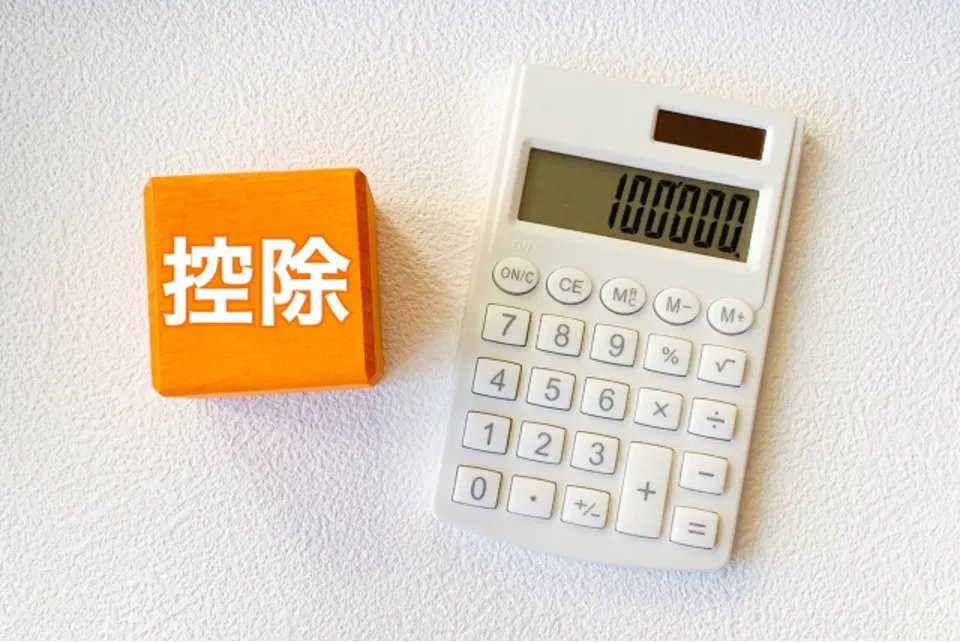
先述のとおり、給与からは税金や社会保険料等、様々なお金が天引きされています。
ここでは、給与から差し引かれる主なお金について、その仕組みと計算方法を解説します。
所得税
所得税は国に納める税金で、年間所得に応じて課される税金です。
会社員の場合、毎月の給与から所得税の概算額が天引きされ、年間の所得が確定する12月に、その年の所得税の過不足を精算する「年末調整」が行われます。
所得税の金額は、基本給や各種手当から社会保険料等を差し引いた「課税所得」をもとに、国税庁が定める「源泉徴収税額表」に沿って計算されます。
税率は5~45%の間で7段階にわかれており、課税所得が増えるほど高くなります。
住民税
住民税は都道府県や市区町村等、地方自治体に納める税金で、所得額に応じて課される「所得割」と、一定の所得がある人に対して定額で課される「均等割」があります。
所得割は前年の所得額に応じて課されるため、原則として新卒で就職した年は住民税が天引きされず、翌年の6月から天引きがはじまります。
住民税にはいくつかの納税方法がありますが、会社員の場合は6月から翌年5月までの分を毎月の給与から天引きし、会社に代わりに納めてもらうのが一般的です。
自治体によって異なる場合もありますが、一般的には所得割の税率は約10%、均等割の金額は年間5,000円です。
社会保険料
社会保険料は、病気やケガ、高齢、介護、失業等のリスクに備えるための公的な保険制度に対して支払う保険料です。
「健康保険料」「厚生年金保険料」「雇用保険料」「介護保険料」等が含まれており、会社員であればいずれも加入が義務付けられています。
保険料は標準報酬月額(給与額を一定幅で区分した基準額)に保険料率をかけて算出され、会社と労働者が半額ずつ負担します(雇用保険を除く)。
給与明細に記載されている金額は、ご自身が負担する分のみです。
以下では、各保険料について解説します。
【健康保険料】
健康保険料は、病気やケガに備える医療保障制度に対する保険料です。
医療機関を受診した際には医療費の一部が給付されるため、自己負担は1~3割に抑えられます。
保険料率は都道府県や加入している健康保険組合によって異なりますが、 概ね10%前後です。
【介護保険料】
介護保険料は、将来の介護に備えて支払う保険料です。
要介護または要支援の状態になった際に、介護サービスを受けられます。
40~64歳の方に支払い義務があり、健康保険料に上乗せして天引きされます。
介護保険料率も一律ではありませんが、2%前後が目安です。
【厚生年金保険料】
厚生年金保険料は、老後の年金や障害年金、遺族年金等、公的年金制度に対する保険料です。
会社員は国民年金と厚生年金に加入しており、これらの保険料が「厚生年金保険料」としてまとめて給与から天引きされます。
厚生年金の保険料率は全国一律で、18.3%です。
【雇用保険料】
雇用保険料は、失業したときの手当や育児休業給付金等に充てられる保険料です。
給与の総支給額に対して一定の保険率をかけて計算され、会社と労働者がそれぞれ異なる割合で負担します。
雇用保険の保険料率は事業の種類や年によって異なりますが、令和7年度の一般事業における雇用保険料率は1.45%(労働者0.55%、会社0.9%)です。
その他控除
会社によっては、積立制度や親睦会費といった独自の項目を控除する場合があります。
これらは税金や社会保険料のように法律で支払いが義務付けられているものではありません。
代表的なものには、以下のようなものがあります。
【財形貯蓄】
財形貯蓄は、会社を通じて金融機関にお金を預ける貯蓄制度です。
毎月の給与から任意の額が天引きされ、自動的に積み立てることができます。
財形貯蓄には「一般財形貯蓄」「財形住宅貯蓄」「財形年金貯蓄」の3種類があり、住宅資金や年金を目的としたものでは、一定の条件を満たすことで利子等が非課税となる優遇措置を受けられる場合があります。
【社員旅行積立】
社員旅行の費用を、毎月の給与から天引きして積み立てる制度です。
旅行実施時の自己負担の軽減を目的として、一定額が徴収されます。
【共済会費・親睦会費】
共済会費・親睦会費は、社員同士の親睦や福利厚生を目的とした会における費用の積立です。
毎月、数百円〜数千円程度が給与から差し引かれ、レクリエーションや慶弔行事等の活動費に充てられます。
収入、所得、手取りの違い

「収入」「所得」「手取り」は同じような意味で使われることがありますが、厳密には異なります。
給与明細や税金に関する理解を深めるためにも、この3つの違いを正しく押さえておくことが大切です。
以下で詳しく解説します。
収入
収入は、税金や社会保険料等が差し引かれる前の総支給額(いわゆる額面給与)を指します。
基本給、各種手当、残業代、賞与等をすべて含めた金額です。
所得
所得は、収入から給与所得控除を差し引いた金額です。
給与所得控除は、収入を得るために必要な経費とみなされるもので、この控除によって課税対象となる所得(=課税所得)を減らすことができます。
手取り
手取りは、収入から税金や保険料等の控除を差し引いた後、実際に受け取る金額のことを指します。
収入により異なりますが、年収600万円以下の場合は総支給額の75~85%が手取り額の目安です。
まとめ

この記事では、給与明細の見方や税金、社会保険料の仕組みについて解説しました。
毎月の給与明細を確認し、その内容や仕組みを理解することは、将来に向けた資産形成の第一歩につながります。
ご自身に合った資産形成の方法を知りたい方は、銀行や証券会社等で専門家に相談するのがおすすめです。
給与明細の内容を理解し、ご自身の収入や支出を把握することで、家計管理や将来の資産形成に役立てましょう。
資産運用のご相談は西武信用金庫へ
西武信用金庫ではお客さまの資産運用のご相談を承っております。